
プロフィール
名前:戦国アイコ
戦国武将とカフェが大好きな会社員
- 特徴:残業は嫌い。仕事の後カフェでまったりするのが大好き。
- 趣味:猫と遊ぶこと。推理小説を読むこと。
- モットー:ほどよく頑張る。
- 好きな食べ物:スウィーツ(特にクリームあんみつ)
- 嫌いな食べ物:梅干し、納豆。


プロフィール
名前:戦国アイコ
戦国武将とカフェが大好きな会社員
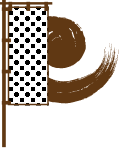 アイコの部屋💖与謝蕪村へインタビュー!(後編)松尾芭蕉に憧れて『奥の細道』を放浪した蕪村が、芭蕉と並ぶ巨匠になれたのは何故?驚愕!その陰の立役者は、明治時代のあの超有名人物だった!
アイコの部屋💖与謝蕪村へインタビュー!(後編)松尾芭蕉に憧れて『奥の細道』を放浪した蕪村が、芭蕉と並ぶ巨匠になれたのは何故?驚愕!その陰の立役者は、明治時代のあの超有名人物だった!
皆さんこんにちは!アイコの部屋の時間です(^^)/
今日も前回に引き続き、江戸三大俳人の一人、与謝蕪村さんをお迎えしています!

蕪村さん、今日もよろしくお願いします!
はい、アイコさんよろしくお願いします。
前回この番組に出演したら、反響大きくてくてビックリしました!
蕪村さんって、職業は画家だったの!?って、何人にも聞かれましたよ~。
江戸時代に売れっ子画家だったこと、現代では全然知られていなかったんですねぇ。
だから今日は、絵のこともガンガンアピールしちゃいます!

【 最上川 】
芭蕉の句:五月雨を集めて早し最上川
今日は、『奥の細道』を巡る東北の旅の話からですね。
そう言えば、芭蕉の『奥の細道』って、どんな内容でしたっけ?
実は私よく知らなくて・・・苦笑
『奥の細道』は、ロングセラーの人気本ですよ~アイコさん!
これは1689年、松尾芭蕉が46歳の時、崇拝する西行さんの500回忌を記念して、東北各地に点在する歌枕(和歌で歌われた名所)や古跡を旅した様子をまとめた、旅行日記です。

【 奥州 平泉 】
芭蕉の句:夏草や兵どもが夢の跡
『奥の細道』は、俳句紀行文の最高傑作と言われているんですよ。
芭蕉が旅したそのルートは、江戸深川を出発し、関東、東北、北陸、中部地方にまで及び・・・
全行程150日(5か月間)2400kmにもなります。

【奥の細道について/奥の細道結びの地記念館サイトより】
http://www.basho-ogaki.jp/hosomiti/about/
へえ~!こんな広い範囲まで旅してたんだ!!
旅の終盤に、敦賀、大垣って、そのまま京の都に行っちゃう勢いだわ!
『奥』でも『細道』でもない気がするww
もうメインロードに近いでしょう。タイトル「おもての大通り」と変えて!!

【 松尾芭蕉像 】
奥の細道、私は、秋田県の八郎潟(はちろうがた)から青森県の津軽にまで、足を運びました♪
芭蕉が訪れ、俳句を書いた場所に自分も行って、同じ景色を眺めながら俳句を書いてみる。
これ、当時の俳句好きの間では、大ブームだったんですよ!
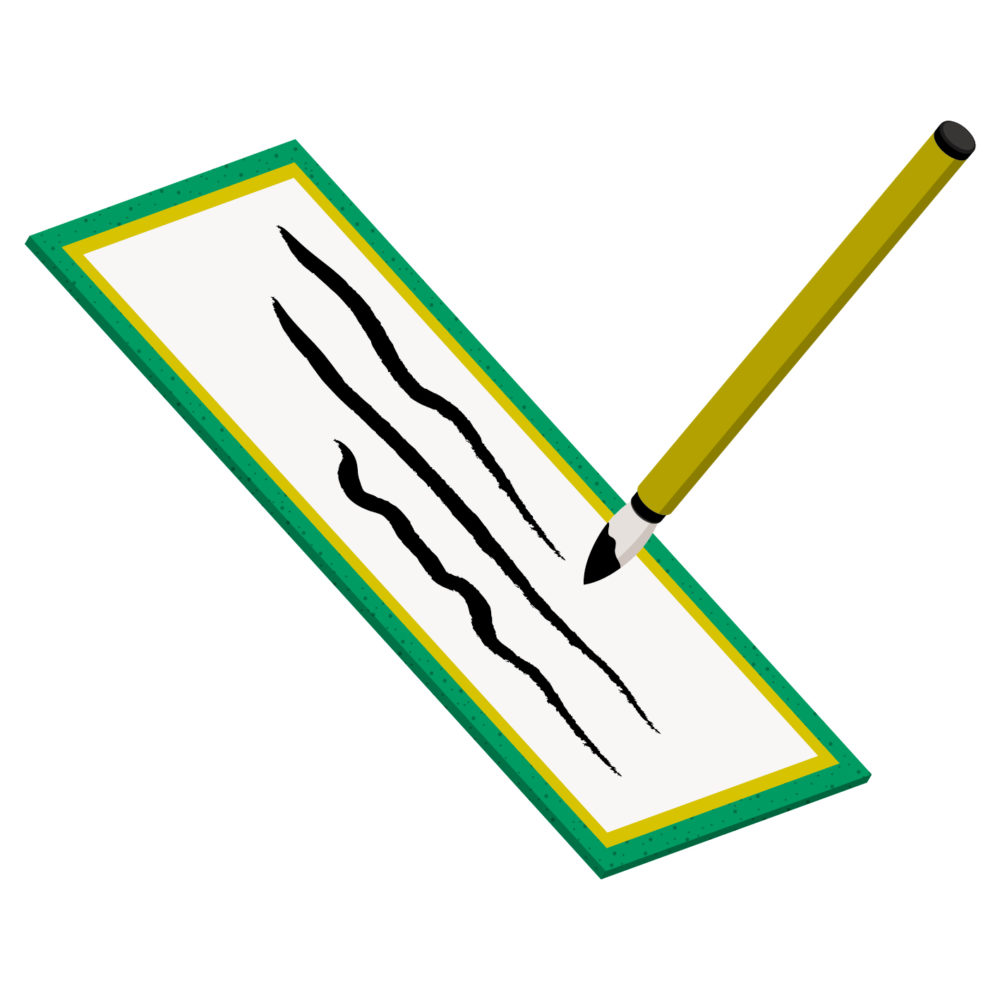
今なら、Twitterでインフルエンサーの芭蕉がつぶやいた場所に、フォロワーが行って、
『芭蕉がいた場所なう』って、喜んでツイートするみたいな感じかな?ww
私は、東北や北関東、江戸など各地を転々とし放浪しました。
綺麗な景色を絵に描いたり、俳句を書いたり、約10年間、バッチリ修行をしましたよ!
放浪・修行生活も10年近く経った頃に、私は新たに決心したんです。
そうだ、京都行こう!
ってね。

JRのCMキャッチフレーズみたい~ww
今度は京都!?なぜですか?
商業の中心は江戸だけど、文化の中心はやっぱ都(京都)なんですよ。
私の絵の才能を発揮できるのは、もう都しかない!!って感じで。
ちなみに当時の京都美術界は、絶頂期でした。
有名カリスマ絵師の円山応挙(まるやま おうきょ)を始め、動物絵で大人気の伊藤若冲(いとう じゃくちゅう)、山水画の第一人者の池大雅(いけのたいが)など、天才達が集まり、しのぎを削っていましたよ。
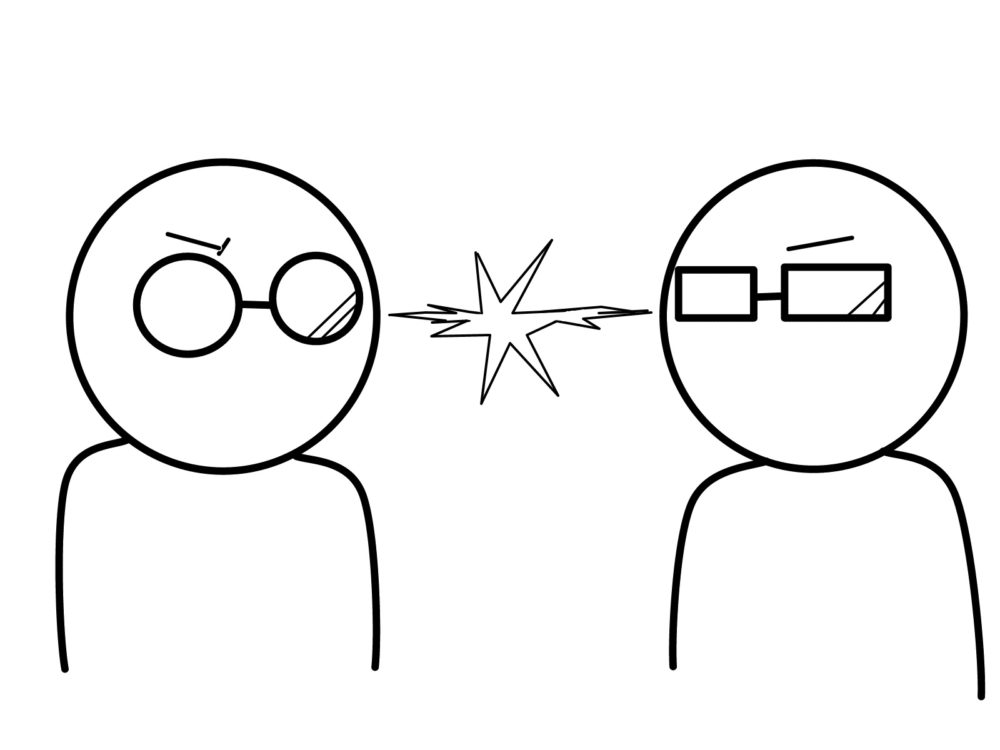
私も、彼らに負けないように頑張りました!ここから私の快進撃が始まりますよ~!!
画家としての仕事は、徐々に軌道に乗り実績も増えて、次第に、屏風など大作を手掛ける機会が増えていったんです。
そしてやっと収入も安定し、45歳の時に結婚をして、一人娘を授かることも出来ました!

それからは家族を養うために、お客が求める売れる絵をひたすら描き続けましたよ!
例えば当時、伊藤若冲の動物画が大人気だったので・・・それを真似て、こんな絵を描きました。

【 与謝蕪村 猛虎飛瀑図/福田美術館サイトより 】
https://fukuda-art-museum.jp/collection
また、池大雅が得意とする山水画も人気だったので・・・それを意識して描きました。
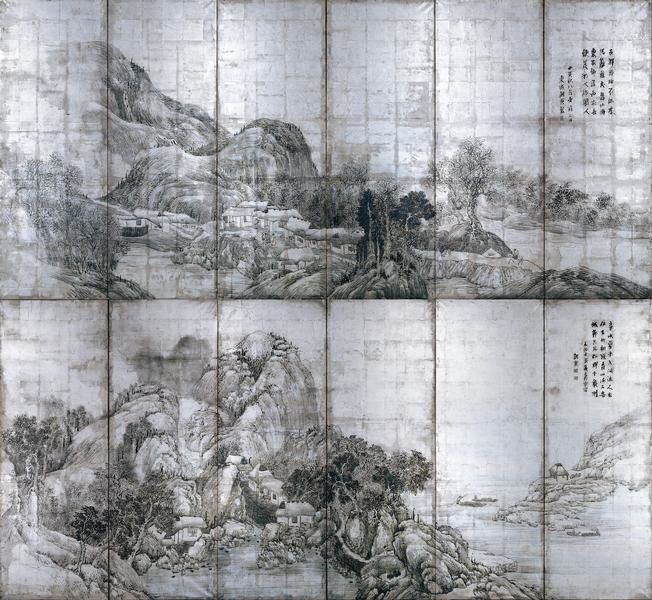
【 与謝蕪村 山水図屏風/MIHO MUSEUM サイトより 】
https://www.miho.jp/booth/html/artcon/00006102.htm
また、屏風好きなファンからの要望で、中国絵画の技法を取り込んだ、こんな作品も描きましたよ。

【与謝蕪村 茶筵酒宴図屏風(ちゃえんしゅえんずびょうぶ)/福田美術館サイトより】
その時々で、求められるままに描き、5種類の画風を使い分けていましたね。
流行やお客様の要望に応じて絵を描き分け、
1人で5種類の違う画風を描けるなんて、技術が素晴らしいですね。
でもね、逆にそのことが私を悩ませたんです。
私は、自分の名を世の中に広める為、大衆に迎合し、絵の道を迷走していました。
結局、他の画風を真似したレベルでは、どこまでいっても私は2番手にしかなれません。
与謝蕪村のオリジナリティって何?
自分だけが描ける絵はないのか?
それを見つけられずに苦しんでいたんです。
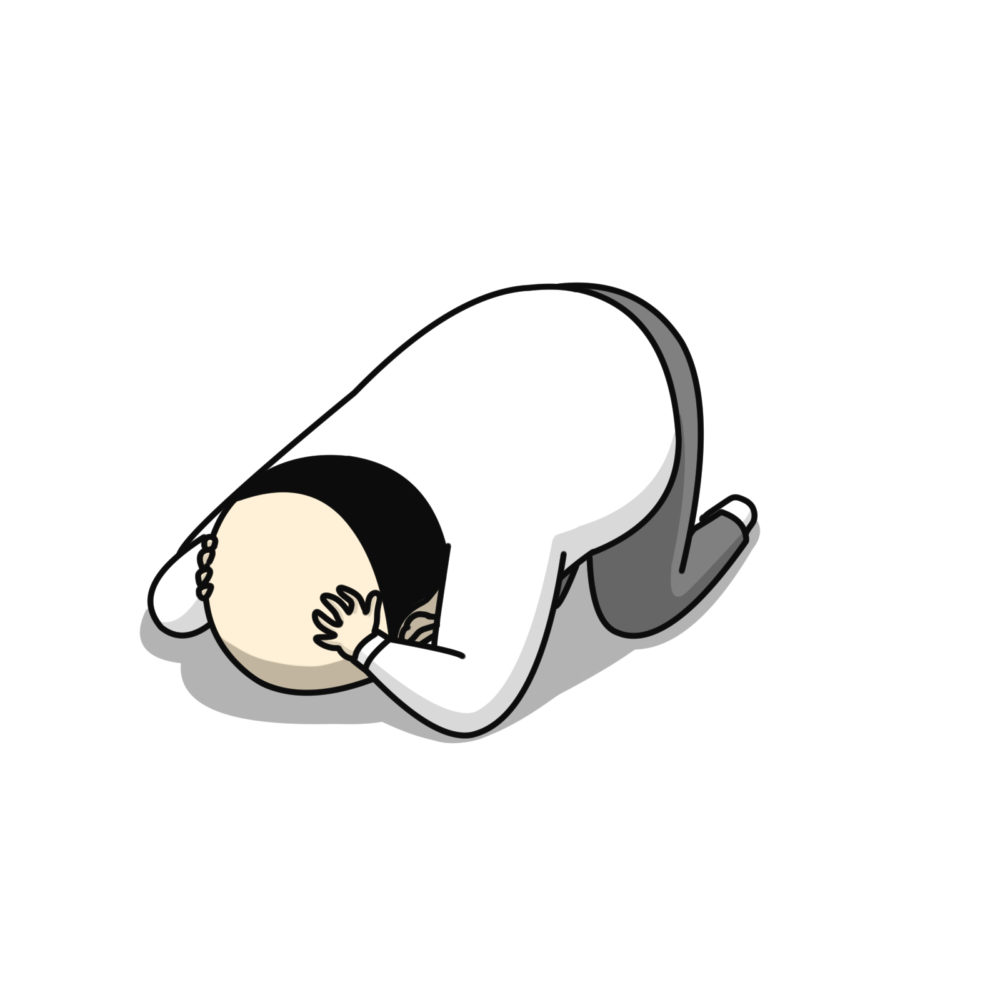
なるほど。
芸能界で、漫才を目指したら、トップにビートたけしがいて、
演歌のトップを目指したら、北島サブちゃんがいた!
じゃあ自分は、どのポジションでトップになれるのか!って悩む感じねww
私にはいつも、あの巴人師匠の教えが胸にありました。
オンリーワンを目指せ!
独自の境地を探れ!
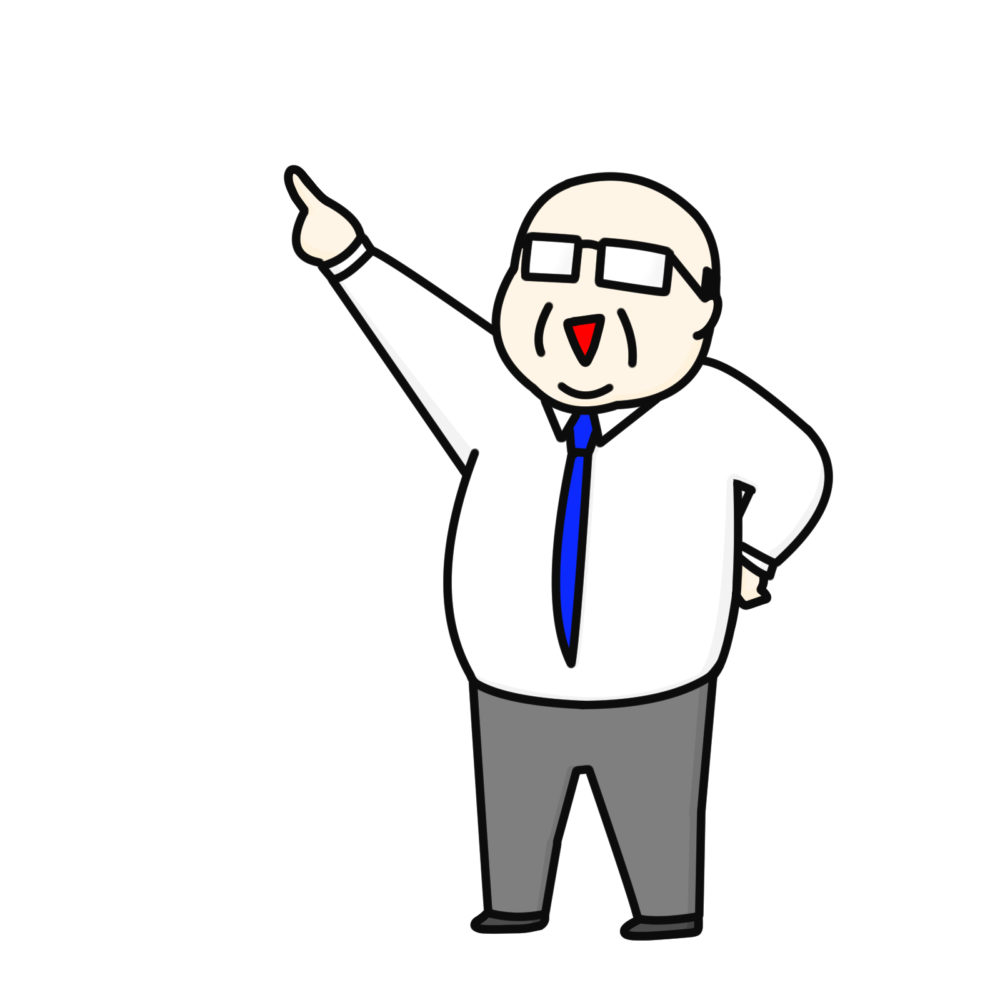
悩み模索した末に、私は気づいたんです!
そうだ、自分は『一流の絵が描けて、一流の俳句が書ける二刀流なんだ!!』
これを生かしていこう!って!
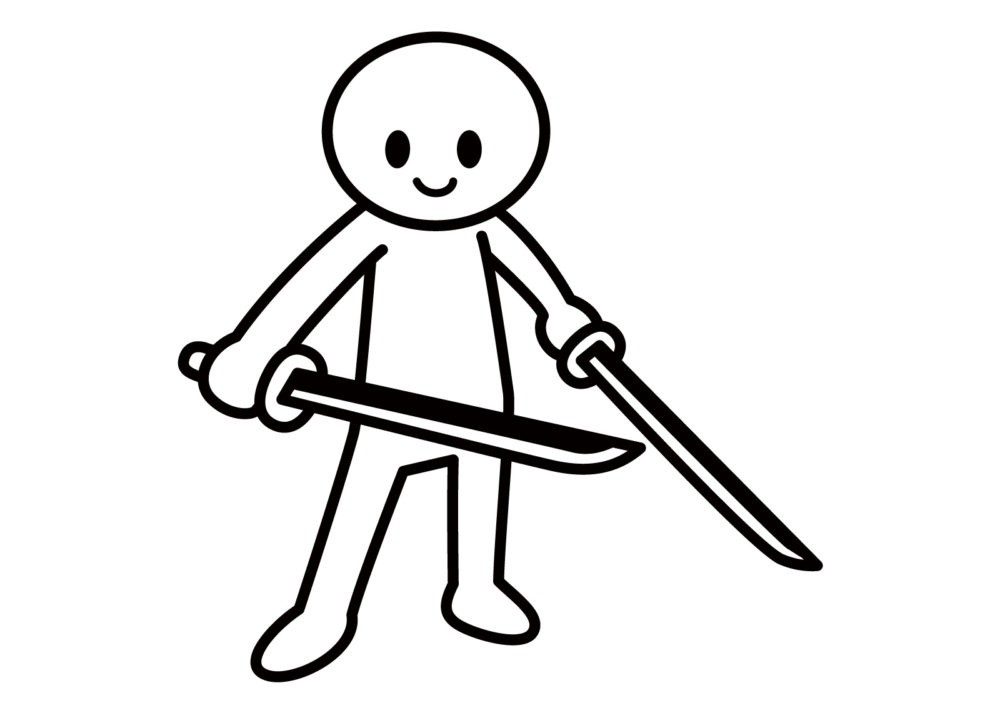
実はそれまでは、本業は画家、俳句は趣味だと2つを切り離していたんです。
でも55歳の時、周りからの推薦で巴人師匠の跡を継ぎ、夜半亭一派の二代目師匠に就任しました。
これを期に自分の意識も変わり、画家&俳人だからこそ描ける “俳画” という新しいジャンルにチャレンジすることにしたんですよ!

【 蕪村筆 俳画 自画賛(岩くらの狂女恋せよほととぎす)/ウィキペディアより 】
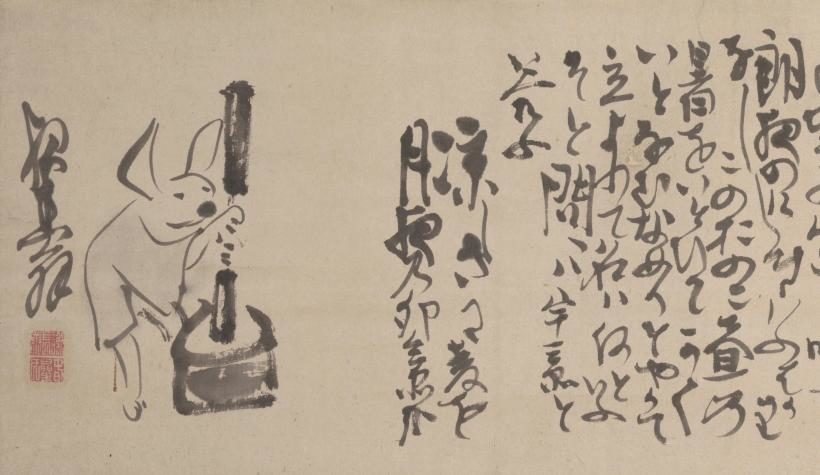
【 与謝蕪村「涼しさに」自画賛(部分)個人蔵/府中市美術館サイトより 】https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/kikakuitiran/buson.html
自分らしさ、独自の境地を見つけたんですね!
今までの画風と比べてシンプル、でもすごく印象に残る気がします。
そうなんです。結局、シンプルな絵にたどり着きました。
今まで、色彩豊で派手だったり、テクニックを駆使しカッコ良さをアピールしたりと様々な絵を描いできましたが、
晩年になって、絵と好きで続けてきた俳句を融合させた時、
『あ~、これが私の求める世界観だったんだ。』って、自分独自の進むべき道に辿り着きました。
ここに行きつくまでに、結構遠回りしちゃいましたけどねー。
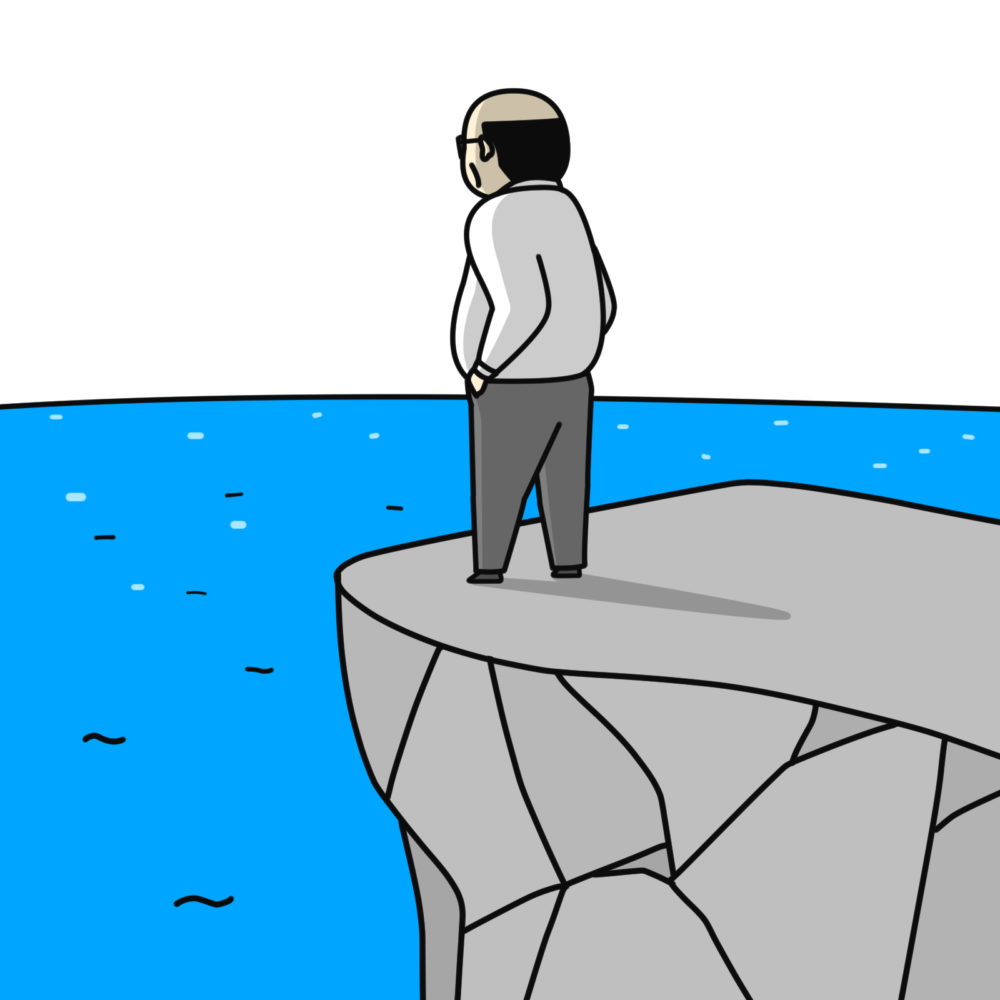
でも、様々な画風を学び真似て描いてきたからこそ、最終的に私の求める世界観へたどり着けたような気がします。
だから、遠回りに思える経験も、無駄ではなかったと思っているんですよ。
素晴らしいですね!
他の追随を許さないオンリーワンの画風も確立し、独特の地位も築き上げた!
こうして与謝蕪村の名は、後世に受け継がれていくんですね!
でも、そんな簡単じゃないんですよ~アイコさん。
私は1783年、68歳で死んだのですが、やはり『去る者は 日々に疎し』ですね。
私って、京都美術界では、五本の指に入る画家だったんですよ!
しかも俳人としても、夜半亭という一派の代表でした!
なのに!!
死後は、
世間から完全に忘れ去られたのです。トホホ💦

まぁ、世の中そんなもんですよね。
でもね、何と100年後に、奇跡が起きたんですよ!!
100年後の1897年(明治30年)、私に再度スポットライトを当てた人物がいたんです!
その人物とは、
この人です!!じゃーん!
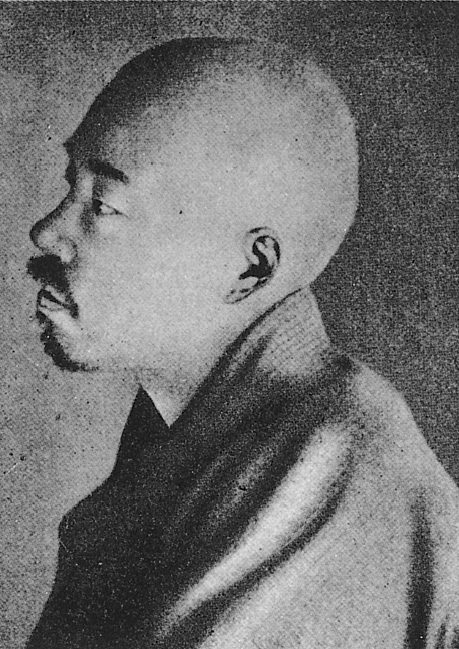
んっ!?
バイきんぐ の小峠ですか?
はぁ!?💢何言ってるんですか?アイコさん!
この人こそ、明治を代表する文学者の一人、正岡子規さんですよ!
💖アイコ:あ~~失礼しました。確か『柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺』の句で有名な人ですね!
💎蕪村さん:正岡子規はね、私について、
与謝蕪村の俳句は、松尾芭蕉よりも優れている!
って世間に発表してくれたんですよ!!めっちゃビックリ~~!!

正岡子規は当時、松尾芭蕉を神聖化する当時の俳人たちに対し、過去の俳句を真似て言葉のテクニックにばかりに走り、目の前の対象をきちんと見て書いていない!
って、痛烈に批判したんです。
チッチッチッ!
俳句ってものを分かってないな~

【 正岡子規 イメージ ねこ】
それに比べて、与謝蕪村の俳句は素晴らしい!!
目の前の景色、出来事を写生するような飾らない言葉で、ありのままの自然体の俳句でワンダフル!!ってね。
正岡子規、スゴイ!勇気あるなぁ!
これって昔、聖子ちゃんが大ブームの時、
『ブリッコの聖子ちゃんより、自然体の美しさの河合奈保子ちゃんがいい!』
って、勇気をもって宣言する!みたいな感じですねww
正岡子規は、忘れ去られた私の俳句の魅力を再発見し、『俳人蕪村』って本まで出版したのです!(Amazonで売ってるよ💖)
その本の中で、私を高く評価し、近代の芸術家としての蕪村像を後世に伝えてくれたんですよ。
あの正岡子規が言うなら、与謝蕪村って素晴らしい俳人なんだろう、って評価に当然なりますよね!
だから・・・
今の時代に、与謝蕪村が有名なのは、
正岡子規のおかげ!!

憧れの松尾芭蕉よりも俳句が素晴らしい!だなんて。お陰で、江戸三大俳人の一人になれたし!
もう正岡子規には、大感謝!!足向けて寝れないですよー!!
なるほど!!
正岡子規がいなければ、与謝蕪村は再ブレイクしなかった!
コロッケがいなければ、美川憲一は再ブレイクしなかった!
さぁ、みんなで暗唱しましょう!!ここ、テストに出ますww
💖アイコ:そろそろ、終わりのお時間が近づいてきちゃいました。
駆け足で蕪村さんの人生を振り返ってきましたが、最後に、令和に生きる私達に何かアドバイスをいただけませんか?
💎蕪村さん:そうですね。
10代のどん底状態から這いあがり、画家・俳人として成功した私から、是非3つのことをアドバイスしたいですね。
1.高みを目指して、自分の武器(強み)を磨き続けること。

私は、何が何でも絶対に絵で食べられるようになる!一流の画家になる!と決心して、その技術を磨き上げてきました。
俳句もまたしかりです。松尾芭蕉や巴人師匠の背中を追いかけながら、俳句制作にも精進したからこそ、独自の境地を確立することが出来ました。
2.人を大切にすること。

巴人師匠に出会ってなければ、間違いなく今の私は無いでしょう。
出会えたことに感謝し、巴人師匠はもちろん、結城や北関東に広がる同門を大切にしてきましたし、絵のお客様、句会の生徒さん、皆さんを大切にしてきたからこそ私も好かれて、今の自分の成功があると確信しています。
3.ありのまま 自然体でいること。

何事も、形式やテクニックは確かに重要だと思います。
私も、様々なものを真似たり追いかけながら、自分を成長させてきました。
でも晩年たどり着いたのは、余計なものを削ぎ落した、ありのままの自分でした。
俳句についても、見た事感じた事を、誰の言葉でもない、自分の感情から湧き出てくる素直な言葉で表現しています。
そうやって私が、感じたままに自然体で、飾らない言葉で書いた俳句だからこそ、
100年後の正岡子規の心に響いたんじゃないでしょうかね。
世の中、ハウツー本やテクニック本があふれているけど、やっぱり最後、人の心を打つのは、
その人らしく『ありのまま 自然体でいること』かもしれませんね。
わぁ~~素敵なアドバイス!!有難うございます!
さて、そんな蕪村さんについて、嬉しいお知らせがあります!
京都市にある福田美術館では、『芭蕉と蕪村と若沖展』を開催中です!!
※2023年1月9日まで
↓ ↓ ↓ ↓
https://fukuda-art-museum.jp/
でも京都かぁ~遠くて行けないよ~という、そこのあなた!
福田美術館では、何と!!VRで美術館を楽しむことが出来るそうですよ☆
お家で楽しむ福田美術館/VRで若冲作品展示の様子を公開!
↓ ↓ ↓ ↓
https://fukuda-art-museum.jp/info/202112272089
よかったら、是非楽しんでくださいね💖
アイコさん、今回は有難うございました。
超人気番組アイコの部屋で、私を詳しく紹介し、
展覧会の紹介までしていただいて、令和の皆さんも私に興味が湧いたと思います。
あなたは私にとって、まさに令和の正岡子規ですよ!
いや~照れますね~ww
こちらこそ、蕪村さんの生き方に刺激を受けました。
お会い出来て嬉しかったです!有難うございました!

さて、今年の戦国アイコのブログは、これで終わりです(^^)/
今年も、読んでいただき有難うございました♪
来年もよろしくお願いしまーす!!
歴史好きの皆さんにとって、来年も、
素晴らしい一年となりますように💖(*^^*)
参考文献:
『蕪村 日本人こころの言葉』藤田真一/創元社
『与謝蕪村 300年の風景』みのごさく